|
「、ルパンたちの次の標的がわかったぞ」 部屋に入るなりそう言う銭形。いつも挨拶もなしにやってくる。 は普段からルパン捜査に加わっている訳ではなく、こうして彼らが狙っているものが確定した時にだけ、銭形がを呼びにくる形で捜査を共にするのだった。彼女にしてみれば、ルパン捜査というのは五右ェ門に会えるという意味でもあり、縁結びの片棒を担いだ銭形としてはと五右ェ門を会わす機会をつくってやらない訳にもいかないのだ。 「どこなんです?」 「スイスの大手銀行だ」 「今回はお宝ではなく、堅実に現金を狙うの?」 「俺に聞かれても知るか」 も彼らの目的がなんだろうとあまり気にならなかった。それは銭形も同じようだ。彼はルパンを捕まえられればそれでいいのだ。 「私にも少し分け前くれないかなあ。新しいバイクもほしい頃だし」 「ふざけたことをぬかすな!」 「だっていちおう、彼は恋人ですし」 そして右手の小指を見つめた。婚約指輪でも結婚指輪でもない、ピンキーリング。ピンキーリングには思いを叶えるという意図が強いようだが、今ある幸せを逃さないという意味もあるらしい。他には厄除けや、仕事成就などの意味合いもあるという。 このピンキーリングはルパンたちがの為に盗んだものだった。最初こそ盗んだものを貰うのは気が引けたが、五右ェ門からの初めての贈り物、しかも指輪のデザインも悪くなかった。むしろ素敵だった。 華美ではないけれど、ピンキーリングという小さな指輪の中に散りばめられた小さな石はどれも希少価値のあるものらしい。その石のフレームとなる金属もまた高価なものだ。 「またそんな指輪ばかり見ておる。さっさと先方に事情を話しに行くぞ」 指輪を見ていると彼を思い出す。今何をしているのだろうと。自分が彼らの計画を調査し始めたということは、彼らはもっと前から計画を練っていたということだ。犯行直前になって互いが同じ国に入国すれば、逢瀬の一度や二度もできないものかと、彼も想像してくれていたら嬉しいと、は思った。 は銭形に促され、しゃっきりと返事もしないまま椅子の背もたれから上着をとって羽織った。 「私が頭取のディートリヒ・バーナーだ。ルパン三世がうちの銀行を狙っていると?」 「はい。ルパン逮捕はICPOの管轄なので参上した次第です」 「君のような女の子に追われるとは、彼が羨ましい」 ジョークなのか本気なのか分からない口調で言われるものだから、は少しだけ照れてしまった。半歩後ろに構えていた銭形に小突かれて今度はが半歩下がり、銭形に出番を代わってもらった。 「そんな流暢な話ではないのです。ここの預金を盗まれでもしたら、おたくは破産ですぞ」 「言われなくてもわかっていますとも警部殿。私はプロですよ?」 普通、『ルパンが来る』と言われた美術館や銀行、宝石商などの重鎮は、警備を厳重にしろ、絶対に盗まれてはならないと慌てふためくものだ。しかしこのバーナー氏はなかなかの落ち着きようだ。スイスというだけあって、自社の警備体制に自信があるのだろう。 「貴方が断ってもこちらはルパン逮捕という国家業務があります。申し訳ないが、協力をお願いする」 「お断りなどしませんとも。さあ、遠慮せず座って」 バーナー氏は銭形とを座らせた。 バーナー氏の年齢は47歳。若くして頭取になれたのは彼の祖父がこの銀行の創設者だからだ。彼の父は早々に他界したが、父よりも金融業の才能があったディートリヒ青年は急な引き継ぎも難なく取り次ぎ、業務も卒なくこなしている。ちなみに未婚。 「コーヒーのお供は何がいいかな。チョコレート?」 「いえお構いなく」 「ダイエット中かい?君はもうちょっとフェイスラインに丸みがあった方がより可愛らしくなると思うがな」 そらまた出た、とは思った。 「ミス・、代わります」 同僚にそう言われ、は時計を見た。まだ犯行予告までだいぶ時間がある。しかし念には念を入れて、銀行内での見張りを強化していた。 は同僚に礼を言い、会議室に構えた作戦本部でコーヒーでも一杯飲もうかと思った。何時までかかるかわからない捜査のためにしっかりと数日前から睡眠はとっていたつもりだったが、少し眠い。 会議室に銭形の姿はなかった。きっとどこかで日本式の張り込みとやらをしているのだろう。 煮立ってしまいそうなコーヒーを紙コップにうつして少しすすったが、その暑さとあまりのまずさにカフェインを採らずとも十分に目が覚めた気がした。 テーブルに置いた紙コップにはほとんど口紅の色がついていなかった。 ルパン一味の計画がわかってから今日まで、まだ彼らには会っていない。もちろん五右ェ門にも。 つまり、もし今日、本当に犯行が行われ、彼らに遭遇することになれば、久しぶりに顔を合わせることになるのだ。 例え仕事中だとしても恋人と会うときは綺麗でいたい。はバイクに乗ることばかりでおざなりにしてきた化粧にやっと興味を持ち、最近、少し高価な口紅を買った。店員に言われるがままに(お客様の肌色にはこの色がよく合います。お顔がぱっと華やぎます。)購入した。 先ほどのまずいコーヒーを飲んだ時、紙コップに色が残っていないことが不安になってはレストルームの鏡の前に立っていた。ついでに用をたしたので洗面に手をかざす前に指輪を外した。高価な金属なのでよっぽど錆びたりはしないと言われたが、大事にしたくていつも水に触れる時は外している。大理石で出来た洗面に置かれた時に響くその小さな響きまでもが愛おしいと思える、恋人からの贈り物。 はスーツのポケットから口紅を取り出し、慣れない手つきで唇に色をのせてゆく。ほんの少しだけ、元の唇の色が隠れ、さりげなく彩を与える。 「早く、来てくれたらいいのに……」 彩と共に艶をまとった唇が小さく動いて、囁き声を発した。こんなにも恋が素敵なものだなんて、知らなかった。 とその時、鏡に移った自分を誰かが羽交い絞めにした。口紅を塗っていたことで反応が遅れ、もがいて振りほどく前に相手の方が優位な体勢にもっていかれた。 は小さく悪態を口走った。羽交い絞めにされたものの、まだ自由のきく足で相手の脛を蹴った。相手は少し怯んだのか後退したが、の上半身を依然つかんだままなのでも一緒になって引き摺られていく。そして、相手の背中がトイレの個室の扉に当たったのか、バタンと大きな音がしても個室に連れ込まれる。 厄除けの意味もある指輪を外した途端にこのザマだ、と思った瞬間、洗面に指輪を置いたまままだ嵌めていないことに気付いた。はっと洗面の方に視線をやると、一瞬の輝きが見えて、すぐに個室の扉が、もう一度大きくバタンと言う音を立てて閉まった。 「さっきの蹴りは痛かったな」 ドアを閉めた音とは違う、ガタンという音がした後、聞き覚えのある声がした。はっとして振り返ると、を羽交い絞めにしていたのはバーナー氏だった。 「私も手荒なことをして申し訳なかった」 「なぜ、どうしてあなたが」 バーナー氏がの拘束を解いたかと思えば、またガタンと音がして、身体が一瞬浮遊する感覚を得る。その感覚は、エレベータそのものだった。どこかへ連れて行かれているのだと、はまだ落ち着かぬ呼吸を落ちつけようとするかのように、乱れたジャケットとシャツを整えた。 「この個室はね、隠し部屋に通じているんです。このパネルに私の手の指紋照合センサがある」 バーナー氏が指差したのは、先ほども使った、トイレを流すときのパネルだった。 「なぜ今まで黙っていたのです。こんな隠し部屋、ルパン等はとっくに調査済みかと」 「『敵を欺くよりまず味方から』ということわざ、君の国のものだろう?」 笑顔でそう言うバーナー氏。ジャケットを整えている時にポケットに口紅が入っていないことにも気付いて、指輪も口紅も後で回収できるのだろうかと、はぼんやりと考えた。 通された隠し部屋と言われた部屋にはたくさんの美女がいた。ここが銀行である為に、勝手に隠し金庫だとかそういういった類のものを想像していたは拍子抜けした。 しかしそれ以上に、美女たちがちっとも動かないのが不気味だった。その部屋は静まり返っていた。彼女たちはなにか談笑するわけでもなく、ただ整然とそれぞれのポーズをとってそこにいるだけなのだ。 悪趣味だと思いながら、一番近くにいたマネキンなのか蝋人形なのかわからぬ美女を見やった。ふわりと良い香りが漂ってくるのが想像できる程の美女だ。 「よくできてますね。まるで本物みたい。彼女たちは実在の人物なのですか?」 「ああ、実在している。まさしくそこにいるじゃないか」 はじめ、バーナー氏の言っている意味がよくわからなかった。だが、よくよく美女を見て見ると、何となく嫌な感じがした。焦点の合わない目の瞳孔は大きく開いたまま。しかし死臭などは微塵も放っていない。 「まさか」 は振り向くと同時に脇から拳銃を抜いてバーナー氏の方に向けた。バーナー氏は大人しく両手を上げている。 「そう、彼女たちはオリジナルだよ」 「さしずめ剥製ってとこ?」 「美しいだろう?」 バーナー氏は誇らしげに美女の剥製たちを見回した。こんな狂気に満ちた部屋に、そしてこのコレクションを作り上げた張本人と二人きりなんて。は早くここから立ち去りたかったが拳銃を下ろす訳にはいかない。 「私もコレクションに加えるって訳?」 「もちろん。でなければここに連れては来ないよ」 降りてきたエレベータはバーナー氏の指紋照合がないと作動しないという。彼を失神させるか、腕をもぎ取るかしないと駄目だろうか。はここから脱出する術を考え巡らせた。 「私なんて、ここにいる彼女たちのように美しくなんてないのに。剥製にする価値なんて」 「東洋人のコレクションはまだなくてね。私に小児趣味はないのだけれど、日本人はなんとも可愛い顔をしている。それに君にはそれ以上の価値がある」 バーナー氏が胸元から何か取り出そうとしたのでは反射的に銃弾を床めがけて一発放った。彼は怯んだ様子も見せず、しかし床に空いた穴を一瞥してから、改めて手につかんだ物をに見せた。にとっては初めて見るものだった。だが、それが何かの器具だということはその特殊な形とステンレスの輝きでわかった。 バーナー氏よりも自分自身の方が銃声に怯えていた。は拳銃をしっかりと構えなおした。 「君のその綺麗な子宮」 バーナー氏は器具をの方へ向け、ネジ巻きになっている機構をくるくると指で回した。クチバシのようになっていた先が、滑らかに開きだす。チャリチャリと小さな金属音がする。 「君は処女だろう。処女どころか、自分の膣に指を入れたことすらないんじゃないか?」 は本当のことを言われて瞬時に頭が熱くなった。 「憶測でものを言わないで。私はもういい歳で恋人だっている」 「その歳で処女だということを恥じているのか?何も恥じることでもないだろう。むしろ誇るべきだ。ここに佇んでいる女達は皆美しいが、その中身ははたして。私の財産や肩書き欲しさに色目を使ったり、駆け引きをしようとしたり。でも君は違う。初めから僕に嫌悪感を抱いていたね」 「なんとなく、ね。この仕事をしていると無意識に人を善と悪の篩にかけてしまうのよ」 「善と悪か。こんなことをしている僕は悪として、それでは君はどっちかな」 彼は相変わらず器具をカチャカチャといじっている。ネジを回して、クチバシを開いたり閉じたり。その動きはの心を無理矢理こじ開けようとでもしているかのようで。 「君は14歳の時、少年事件に立ち会った」 「なぜ、それを」 「君を初めて見た時から君が気に入ってね、調べさせてもらった」 うちの銀行に持ち込まれる金がどんな金なのか、汚れた金なのか、それを調べるよりも簡単に君の情報は調べがついた。バーナー氏が静かに語り出した。 「目の前で嬲られる男、その男の横で代わる代わる陵辱される女。その光景は今でもまざまざと君の中に残っているんじゃないか?」 そうだ、その通りだ。私はただ呆然と見ていることしかできなかった。男を嬲る狂気もなければ、女を犯す凶器も持っていない。そして、仲間を制止する勇気もなかった。今思えばそんなことばかりが浮かぶ。しかし、あの時に感じたのは恐怖だけしかなかった。 権力を持つ父親。その父親に従うことしかできない弱い母親。父親の意念のままに幼児の頃から進学校へのエスカレータに乗せられる自分。 夫を失望させない娘に育てなければと強迫観念に襲われる母。父に叱られたくない。父に詰られる母を見たくない。そうして見つけた最善の道は、父が敷いたレールだった。 しかしそのレールのポイントを自ら切り替えることができるのだと、教えてくれたのが、不良少年たちだった。 今まで我慢していたものが弾けるかのように、今までしてきたことと真逆のことばかりをした。父を憤慨させ、母を病ませた。承認欲求の果てが、彼等との悪事や夜遊びだった。 「同じ女性として、目の前で犯される女を見て何を感じた」 「狂気よ……」 はあの時の情景が目の前に浮かんで目が霞んだ。構えた銃口が男から揺らいでいく。 「若者は自分たちを大人だと思っているようだが、大人になってみればどれだけ幼かったかがよくわかるものだ」 「それが何だっていうの」 「それこそ君がさっき言った狂気だよ。少年たちは場の雰囲気に互いが互いに便乗して犯行がエスカレートしていった」 「そうよ。だから何なの」 「君達の間に性的な関係はなかったということだ。仲間だった少年達は、唯一の雌である君に手をつけるのは“抜け駆け”、違反だと暗黙のルールがあった」 「仲間でもリーダーという存在はいるわ」 「そうなんだよ。そのリーダーが君に手を出さなかったら、誰も手を出せないじゃないか」 「私は……」 あの頃の自分に性の知識がなかった訳ではない。生理だってとっくにきている年齢だ。それでも、同じような年齢の男子を性的な目で見るような気持ちは微塵もなかった。 事件の時、犯される女はまるで実験台のようだった。少年たちは皆が皆、童貞のようで、性行為の知識はあるにしても挿入には手間取っているようだった。結果、挿入から射精までを成し遂げたのは1人だけ。他の奴らは女の身体を好奇心のままに弄り好きにして自分の手で自分のものをしごいていた。 「もう、やめて……」 あの時の恐怖が蘇って凄まじい吐き気が襲う。うまく呼吸ができていない気がして、少し膝を曲げたらそのままその場に崩折れてしまった。背中を丸めると少しだけ呼吸が楽になる。 「でもそうだ、今の君には侍の恋人がいるんだった」 自分の動悸の音がやけに響いて、男の声は僅かにしか聞こえない。それでも、声とは違う周波数のチャリチャリという金属音だけは聞こえてくる。 手の感覚はもうほぼ麻痺していた。拳銃を構えているのか構えていないのか、それもよくわからない。 「もしその彼が君の綺麗な子宮を汚していないか、確かめない訳にはいかないな」 しゃがみ込んだ前屈みの自分を、バーナー氏が床にそっと組み敷くのがわかった。仰向けになった途端に吐き気が急激に増して、少しだけ溢れた吐瀉物が自分の顔にかかった。 彼が何かを言って、腰のあたりで何かがもぞもぞと動いた。顔にかかった吐瀉物を拭われる。スラックスのポケットに入れてあったハンカチで拭ったようだ。だがその後もまだもぞもぞと腰のあたり、腹のあたりで何かが動いている。 「これは膣鏡と言ってね。産婦人科に行ったことはないかね?膣に挿入して、このネジを回せば開いて見ることができる」 微かに聞こえたその言葉と涼しくなった下腹部に意識をしっかりせねばと、理性が警告を鳴らす。 拒否の声を出して状態を起こそうとすると、先ほど吐瀉物を拭ったハンカチを口に押し込まれた。後頭部を床に打ち付けたが、床に敷かれた毛足の長い絨毯のおかげでそこまで痛みはなかったが脳が揺れる感覚はあった。 「もうやめて……お願いだから……」 あの時の、犯されていた女の人と同じ言葉を発していた。それでもはなぜだか、こうなることを自分が望んでいたのだと、どこかで感じた。 自分で壊すことのできなかった己自身を、誰か、ぐちゃぐちゃに壊してくれないかと、ずっと願っていた気がした。 ルパン一味がアジトとしておいているアパルトマンの一室に不二子のヒールの音が響いた。 「あら出掛けるの?」 「そ。お仕事」 ルパンは小さなメカからアナログなロープなど、様々な仕事道具をナイロン製のボストンバッグに入れているところだった。 せっかく来たのに無駄足かと落胆しかけた不二子だったが、仕事と聞けば、その内容によってはこの後嬉しいことが待っているかもしれないと急に胸を躍らせた。しかし、彼らが乗り込むのがバーナーの銀行だと聞いて眉間に皺を寄せる。 「あのサイコじみた変態頭取?あいつが触れたお金なら私いらないわ」 「お前あいつのこと知ってんのか?」 「逆にルパンがそこまで調べついてないのが驚きよ。あの男はね、言い寄って来た美女たちを剥製にして地下の隠し部屋にコレクションしてる超ド級の変態よ。そのへんの殺人犯よりもっと凶悪ね」 それを聞いて、仕事前の瞑想をしていた五右ェ門が立ち上がった。 「それは誠か」 「なあに五右ェ門、が剥製にされるんじゃないかって思ってるの?」 「当たり前だ。拙者たちがあの銀行に盗みに入ると情報が知れている以上、彼女は捜査でその男と接触しているはずだ」 そわそわとしている五右ェ門とは対照的に不二子は笑みを零している。 「大丈夫よ。あいつが剥製にするのは美女だけ。みたいに貧相な体つきの女の子は狙われないわよ」 不二子のを酷評するような言い方に五右ェ門は大声でどなりたいところだったが、そこで荷造りをしていたルパンが厳しい声で言った。モニターを見ながら。 「不二子、その隠し部屋ってのはどこにあるんだ」 「女子トイレの個室がエレベータになってて、その地下よ」 それを聞いてルパンが小さく悪態をついた。それから不二子と五右ェ門の方に自分が見ていたモニターを差し出した。そこには銀行の見取り図があり、そこに点滅する一つの光。 「やばいな、20分くらい前からこっから動いてねえ」 それは五右ェ門がに渡した指輪に付けられたGPSの反応だった。 「私のお腹、どうなってますか」 目覚めて直ぐに尋ねた。 以外にも意識を失う前のことをはっきりと覚えていて、自分が今どこにいるのかもだいたい予想がついた。 「大丈夫だ。どこも怪我はしていない」 五右ェ門の声が聞こえて安心すると同時に、引き起こされる疲労感に体が重くなる。 「私、処女なの」 急にの口から飛び出した言葉に五右ェ門は動揺した様子は見せず、湯飲みに入った白湯を彼女に差し出した。上体を起こしたの背中に手を回そうとしたが、彼女はそれを制した。 「あの男がね、私を処女だと言い当てたの。事件のことは調べればいくらでもわかってしまうのは承知していたけれど、あんなふうに煽られたのは初めて」 はそう言うと口先を尖らせて少しだけ白湯をすすった。何の味もしないはずのただの白湯だったが、ほのかに苦味を感じる。 「そりゃ、この歳になるまでに恋人らしい人は何人かいたけど、どの人とも体の関係を持ったことはないの。どうしても、日本で起こした事件の被害女性に後ろめたくて」 「お主はその女性に手を下していないのであろう」 は「そうだけど」と僅かに聞こえるような音で呟いた。 暖かい部屋で恋人と二人、何気なく過ごしていて、キスをして、そのまま身体をなぞられる。そのことを心地良いと思い、もっと欲しい、もっと、と思ってしまわない訳ではない。しかし不と、必死にどこかへ追いやったはずの罪が顔を覗かせ、恍惚を待ち望む私の表情を伺うのだ。 そうすると途端に恐怖が襲ってくる。自分が今得ようとしている快楽は、あの時の少年たちが被害女性にぶつけた欲となんら違いがあるのだろうかと。 その行為に、愛があれば良いのか。愛があれば、正当化されるのだろうか。 五右ェ門がの手から湯呑をとる。 白湯をすすって僅かに湿り気を帯びたの唇に、五右ェ門の唇が触れる。 五右ェ門が地下の隠し部屋に着いたとき、の下半身を包んでいた衣服は取り払われ、あられもなく開かれた両足の間に顔を埋める男の姿があった。 音もなく隠し部屋にやってきた訪問者に男が振り向くとほぼ同時に五右ェ門は男に斬鉄剣の切先を突きたてた。 「君は、彼女の恋人だな」 意外にも男は狼狽える様子もなく声を発することができるようだった。 刀の刃先は、声を発したことによって動いた彼の喉元に僅かに擦れ、つーっと一筋の血が首筋を走った。 男の背後に見えるの脚の付け根には銀色の器具がはめ込まれていて、彼女の膣壁を押し広げ、その奥までが容易に伺えた。そこにあるのは桃色と乳白色の柔らかそうな肉だった。 「それを外せ」 「君が彼女の処女を頂くとは、悲しいことだ」 男は五右ェ門の指示に従うどころか、五右ェ門の言葉すら無視しているようだった。 「君も知っているだろう、彼女の過去を。彼女は今も苦悩している」 「外せと言っているのが聞こえないのか」 「貴様こそ聞こえないのか。彼女が望んでいることが」 五右ェ門は、男が何を言っているのかさっぱりわからなかった。 「彼女は自分の過去の罪を悔い、警官として邁進しているようだが、本当に彼女がそれで過去の罪と向き合えているとは思えない。彼女の真意は、罰を求めている。見ればわかる、この肉の疼きを」 そう言って男はの膣へと視線を向けた。確かに彼の言うように、桃色の肉が不規則にひくつき、白濁とした体液をすべらせている。 「人は誰でも罪人だ。それなのに彼女は親に強制された幼児期と青年期のせいであまりにも罪を恐れている。そして罪に立ち会ったあの夜の出来事が、彼女により罪を恐れさせた」 「それはわかっている」 「では、罪を負いたいという感情は、君には理解できるかい?常に罪人である君には理解し得ない感情かな」 男はの膣から滴ろうとしている蜜を指で掬い取る。五右ェ門が斬鉄剣を握る手に少し力が込められる。 「罪の味は、蜜の味」 男は指先で掬い取ったの体液を天井に備えられた間接照明にあてて照りを確かめるように見ている。少し白い濁りを帯びた体液が指先から垂れ落ちそうになる。 「彼女は自分で自分の罪を裁けずにいる。どうすれば自分の罪に相当する罰を受けられるのかわからないんだ。しかし男の僕らにはその術がわかる。男には生まれ持った凶器があるからね」 ここまで言えば、どうすればいいのか、君にもわかるだろ? 男は不適に笑い、指先から滴り落ちたの体液を舌で受け止めようと口を開き、舌を伸ばした。 男の舌先にの体液が落ちるのを待たず、五右ェ門は男の首を斬り落とした。 胴体からごろりと落ちた男の頭と、頭を失って首から吹き上がる血飛沫にの体液は弾き返され、混ざり合う。男の胴体も少し震えながら頭を追うようにごとりと横に倒れ、勢いの弱まりはじめた血の流れを床に満たしてゆく。 五右ェ門は少し臆しながらもの膣から器具を抜きとった。 初めて見たの陰部は穢れもなく、彼女の茂る陰毛に覆われていた。器具を抜いた際に彼女の膣と器具とを透き通った体液が糸を引き、独特の雌の匂いを漂わせた。 男の温かい血の噴水を浴びたの瞼がピクリと動いて、五右ェ門は彼女のずり下げされたショーツとスラックスを元に戻すと抱きかかえ、斬首された男の死体を残してエレベータに乗り込んだ。 エレベータのドアが閉まる時、部屋に佇む女たちが微笑んだように見えた。 バーナーの死と彼のコレクションの発覚により、ルパン捜査どころではなくなったICPOは陣営が乱れた。その隙にを現場から遠ざけ、ルパンたちのアパルトマンに避難させたが、現場から唯一がいなくなったとなれば何かしら関与したことなどすぐに推測されることだろう。 幸い、銭形がICPOにいるお陰でが現場から姿を消したのはルパン一味に人質として捕られたからだという説で通してもらっているが、すぐにここにも足がつきそうだ。 五右ェ門の唇が離れ、息を吸い込むと、久しぶりに感じる愛おしい人の香りに胸が震える。 は寝かされていたソファから起き上がった。 濃紺のスーツとグレーストライプのシャツにバーナーの血がびったりと滲み込んでいる。早く着替えたい。 「少し歩いてから本部に連絡するわ。その間にあなたたちはずらかるといい」 ハンガーにかけてあったスラックスと同じ色のジャケットにも血がついている。それを羽織る気にはなれなかったが、シャツについた血を隠すには、まだ血の色の目立たないジャケットを羽織る方が良さそうだった。 「もう、行くのか」 「帰って早くシャワーを浴びたい」 「湯ならここにもあるではないか」 五右ェ門は少し強い口調だった。 は五右ェ門の口調に慄いた。普段はこんなふうに、自分の感情を振りかざして相手に恐怖を与えない人なのに、と。 慄くに、五右ェ門は再び口付けた。先ほどよりも強く、乱れた様子で。 「待って、今なの?」 五右ェ門が何をしようとしているのか、にはわかった。口付けは息つく間もなく激しさを増し、血に汚れた衣服は慌ただしく脱がされ始めていた。 バーナーに膣鏡を差し込まれたことはの記憶には残っていて、その後のことはよく覚えていなかったが、膣やその入り口はひりつく様な小さな違和感を感じていた。それなのに、今からそこへ五右ェ門の男根を挿入するのを想像すると、一気に肌が粟立つ。 の肌に手の平で触れている五右ェ門にはその鳥肌の感触もわかるはずだろうに、行為を中断する様子はない。 五右ェ門はの身体から衣服をすべて剥ぎ取ると抱きかかえて風呂場へ連れて行った。衣服を捨てても身体に染みついた血の臭いが気に障る。 勢いよく蛇口をひねられ、シャワーヘッドからまだ冷たい水が降り注ぐ。は小さく悲鳴をあげた。鳥肌が落ち着き始めた毛穴が、再び隆起する。 が冷水に震えている間に五右ェ門も素早く裸になり、彼女の目の前にその男根を露わにした。はそこから目を逸らし、しゃがみ込んだバスルームの床の模様に目をやる。少しずつ温かくなりはじめた水が身体に残った血を洗い流し、タイルの上を流れていくのが見えた。 あそこから、血は出ていないだろうか、と気になって自分の股に目を向けると同時に、五右ェ門の手が股に伸びていた。 「っ」 ずっと仕舞い込んでいた感覚に、声が詰まる。 五右ェ門はを立ち上がらせ、向い合せると胸に吸いついた。五右ェ門の手は背中には回っておらず、両方の手はそれぞれの身体をまさぐることに忙しいようだ。 の身体は感じ始めた快楽を自分の身体では受け止めきれず、背後のバスルームの壁に身体を預けた。 見下ろすと髪を濡らした五右ェ門が赤ん坊のように自分の乳首に吸いついていた。反対の胸も大きな手の平で揉まれながら、指先で乳首をつままれている。 下に降りた方の手はの濡れた陰毛をかき分け、ぷっくりとした大陰唇の間に指を割り込ませる。陰核に指先が触れると子宮の位置がはっきりとわかるようだった。子宮が震えて、そこから全身へと波紋が広がる。 膣口に指が触れると、自分でもそこがぬめりを帯びていることがわかる。五右ェ門の男らしい指が、何か膜でも覆っているかのようになめらかに滑り込んでくる。 先ほどバーナーに膣鏡を入れられたことで違和感を感じていた膣はもう快楽に麻痺して、五右ェ門の指を欲していた。 しかし五右ェ門はただ確認しただけかのように膣から指を引き抜くとしゃがみ込み、の右足を持ち上げて自らの肩に膝裏をのせると、間髪入れずに彼女の陰核に吸いつき、甘噛みした。 「あぁっ……」 は一瞬にして絶頂に達し、腰を震わせてながら崩れ落ちた。 崩れ落ちてバスルームの壁に預けた背中がじりじりと落ちていくのを五右ェ門はの女陰に口付けたまま支えた。 それからの身体を反転させ、彼女の両腕を後ろでに片手でつかみ、腰をもう片方の手でしっかりと掴んだ。そうさせずともの腰は五右ェ門の方へと突き出る形になり、湯のしたたる尻の間で肛門がひくついている。 は五右ェ門に引っ張られている両腕と、バスルームの壁に押さえつけた自身の頭でなんとか体勢を保っている。 そして、絶頂を感じてから間もなく、まだひくひくと痙攣を繰り返している膣に五右ェ門の男根が押し入る。先ほど一瞬だけ入れられた指とは比べられない程の圧に、は思わず声が漏れる。 最初からの様子を気にしない激しいピストン運動に、の頭はズンズンと壁に押し付けられ、口から漏れる吐息と喘ぎがすぐ近くの壁に跳ね返ってやけに自分の耳にリアルに聞こえる。それが余計に快楽に拍車をかける。 「バーナーに捲し立てられて、あの時、ずっと私はこうされたかったんじゃないかって、感じた、気がしたの」 が言い終えて振り向くと五右ェ門が口を開けて彼女の口に吸いつく。舌を入れ、もそれに応えて舌を絡ませ、二人の唾液が湯に混ざって流れる。 結合した互いの性器の間からも、湯を浴び続けているにも関わらず、絶えずぬめりを帯びた体液が溢れ出して止まらない。シャワーと二人の息遣いで聞こえないが、性器と性器が擦り合っている音が容易に想像できる。 スムーズに何の支障もなくピストン運動が繰り返される五右ェ門の亀頭が時折、奥の方に当たっては声を詰まらせる。 「こんな私なんて、気付きたくなかった。でも、こんなに、心地がいい」 後ろでに掴まれていた手はいつの間にか解放され、の腰は五右ェ門の両腕にしっかりと抱えられている。の手は結合部の様子を伺うように自身の膣口や五右ェ門のつけ根をなぞっている。 二人が結合していることが手に取ってわかり、五右ェ門のペニスが恐ろしい程に堅く、肥大していることがわかる。その肥大したペニスが自分の中に出たり入ったりすることが、とてつもなく心地良い。 は快楽に咽せながら、背後から突き上げてくる男はきっと誰でもよかったんじゃないかと、邪推した。 遠くからサイレンの音が聞こえてくる。 はベッドで横になっている気怠い身体を起こし、完全には血が落ちず、泥水で汚した跡のようになってしまったワイシャツを着た。生地の薄いショーツは辛うじて乾いていたが、ワイシャツはまだ少し湿っている気がした。 「セックスして世界が変わったなんて思うの、子どもみたいで恥ずかしい」 そう言うはいくらか吹っ切れたような顔をしていた。 「バーナーに何か言われたんですよね。じゃなきゃ貴方はバーナーを殺したり、その直後で処女だと告白した私をあんな風に犯さない」 「とても処女の反応のようには思えなかったが」 五右ェ門は窓から外の様子を伺いながら答えた。彼の表情を赤と青のパトライトが照らす。 「迎えが来たようだ」と囁いて、五右ェ門はスラックスに足を通したをそっと抱き締めた。 「拙者がしたことは、間違っていなかったのだろうか。まるで、お主がいなくなってしまうのではないかと、不安で仕方がない」 は五右ェ門の消え入りそうな声を聞きながら、スラックスのボタンを閉めた。 「貴方らしくないですよ。そんな弱音」 「お主にだからこそ、こんなことが言えるのだ」 「さっき、世界が変わったって言ったじゃないですか。それに、元々世界が違い過ぎる」 サイレンの音が止んだ。窓から差し込むパトライトの煌めきが一層強くなる。 は五右ェ門の頬に唇を寄せ、身体を離した。 「警官と泥棒。またどこかで会えますよ、会おうと思えば」 アパルトマンのエントランスのドアが開く音がして、階段を上がってくる慌ただしい足音も聞こえる。バンッ、と音がして、寝室の方へとどんどん足音が近づいてくる。 離れた身体を五右ェ門が再び引き寄せた。 の腕を後ろ手に組み、腰から抜いた太刀を彼女の首筋に沿わす。は目を閉じた。 「警察だ──」 寝室のドアが弾かれ、拳銃を構えた警官が数人雪崩込んできた。 五右ェ門の身体がすっと、から離れていく。耳たぶに残る吐息と、「愛している」という囁きを残して、五右ェ門は窓から飛び降りていった。 一人になったはその場に佇み、五右ェ門の後を追っていく警官たちを見過ごした。 どんどんと、五右ェ門と触れ合っていた箇所の熱が消えてゆく。 は背後の五右ェ門が体当たりして割れた窓ガラスの破片の残滓を拾い上げ、首筋にあてがった。 世界が変わったなんて嘘だった。気が紛れたのは与えられた快楽に没頭していた一瞬だけ。それが終われば、ただ虚しい。ただただ虚しく、余計に消えない罪の重みを感じるだけだった。 だからこそ、あの快楽を早くも再び欲している自分がいた。 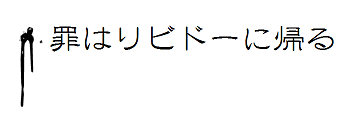 |